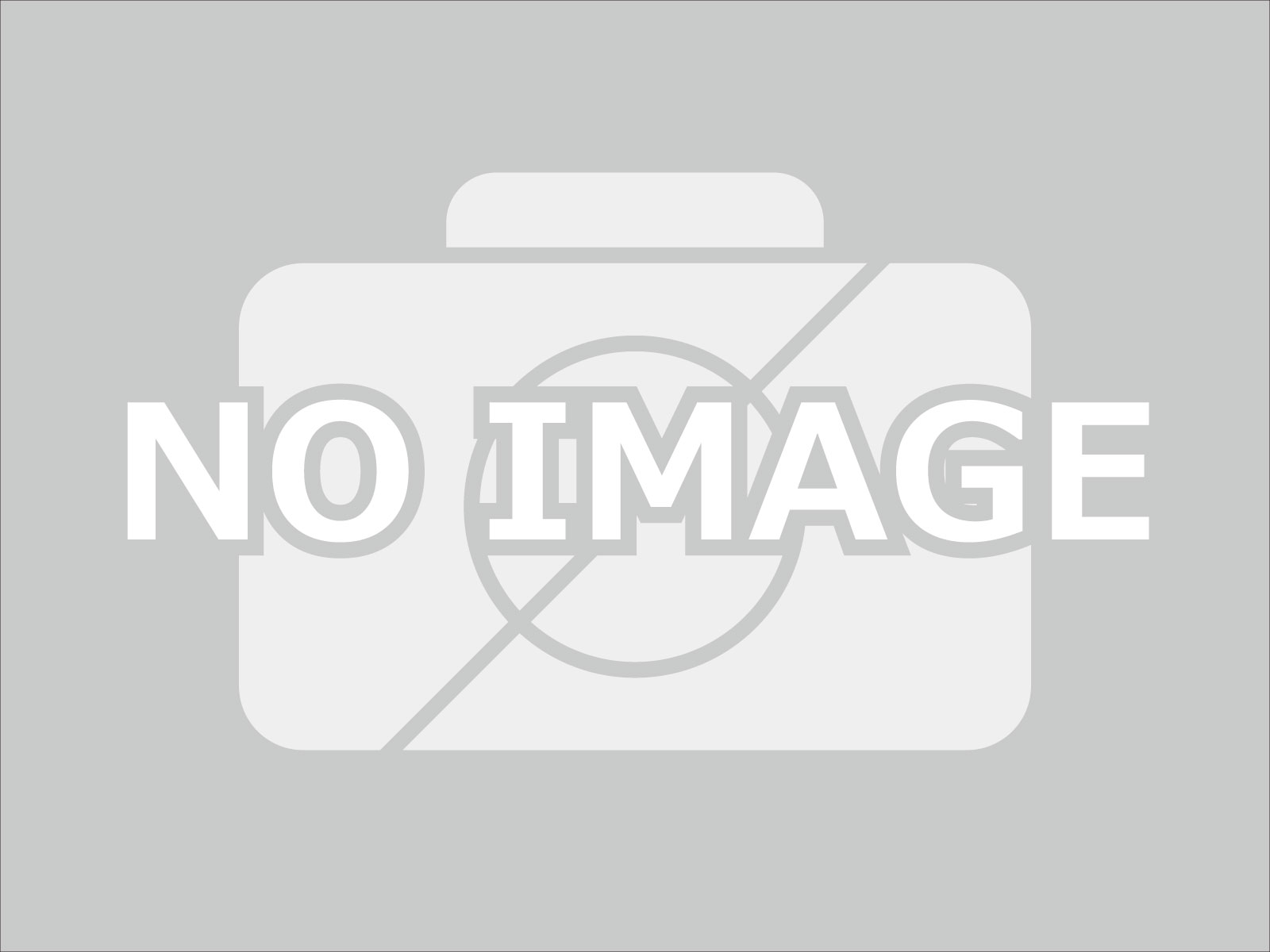触れば三日で死ぬ…伊勢平野に伝わる日本最強クラスの呪物「呪われた灯籠」 三重県伊勢市の、のどかな田園風景の中に、一つだけ異質な空気を放ちながらぽつんと佇む古い石灯籠があります。地元で「呪われた灯籠(のろわれたとうろう)」、あるいは「呪いの石灯籠」と呼ばれるこの物体は、物理的な恐怖ではなく、
...
触れば三日で死ぬ…伊勢平野に伝わる日本最強クラスの呪物「呪われた灯籠」
三重県伊勢市の、のどかな田園風景の中に、一つだけ異質な空気を放ちながらぽつんと佇む古い石灯籠があります。地元で「呪われた灯籠(のろわれたとうろう)」、あるいは「呪いの石灯籠」と呼ばれるこの物体は、物理的な恐怖ではなく、触れた者に確実な死をもたらすという、日本でも最強クラスの呪いがかけられていることで知られる、極めて危険な心霊スポットです。その呪いの強さは、地元住民はもちろん、全国の心霊マニアをも震え上がらせています。
心霊スポットとしての呪われた灯籠:朝比奈三郎の強力な呪い
この石灯籠が心霊スポットとして恐れられる理由は、戦国時代にこの地を治めていた武将によってかけられた、あまりにも強力で具体的な「呪い」の存在にあります。それは「この灯籠に触れた者は、三日以内に原因不明の病や事故で必ず死ぬ」というもの。この呪いは、単なる言い伝えや噂として片付けるにはあまりにも多くの犠牲者を出したとされ、現代に至るまでその効力は全く衰えていないと信じられています。
歴史的背景:隠された財宝と朝比奈三郎の怨念
この呪いの伝説は、戦国時代にまで遡ります。当時、この一帯を支配していた朝比奈(あさひな)氏の当主、朝比奈三郎義秀(さぶろうよしひで)は、戦乱の中で一族の再興を願い、莫大な軍用金をこの地のどこかに隠したと言われています。
そして、その財宝のありかを示す目印として、あるいは財宝を守るための呪いの依り代として、この石灯籠を建てました。義秀は、自らの命が尽きる間際に「もし我が財宝を狙い、この灯籠に触れるような不届き者が現れたならば、我が一族の怨念の全てをもって、末代まで祟り殺してくれる」と、凄まじい呪詛を込めたと伝えられています。以来、この灯籠に手を出そうとした者は、ことごとく謎の死を遂げたとされ、誰も触れることのできない禁忌の対象となったのです。
怪奇現象・体験談:触れた者に訪れる確実な死
この場所で語られる怪奇現象は、霊の目撃談よりも、呪いに触れた者に降りかかる災いが中心です。
- 三日以内の謎の死 この呪物を象徴する、あまりにも有名な現象です。過去、この呪いを迷信だと信じなかった者や、肝試しで灯籠に触れてしまった者が、その直後から原因不明の高熱や体調不良に見舞われ、三日を経たずに亡くなってしまったという話が数多く語り継がれています。事故死や突然死であったケースもあると言います。
- 原因不明の車両トラブル 灯籠に近づくだけでも、車のエンジンが停止したり、ライトが消えたり、帰り道で必ず事故を起こしたりといった、原因不明の車両トラブルが多発すると言われています。これは、霊が「来るな」と警告しているのだとされています。
- 武士の霊 深夜、灯籠の周りを甲冑姿の武士の霊が守るように徘徊している姿が目撃されています。これは、財宝を守り続ける朝比奈三郎義秀本人か、その家臣の霊ではないかと言われています。
現地の状況・注意事項:絶対に触れてはならない禁忌の存在
- 現在の状況 呪われた灯籠は、現在も田んぼのあぜ道にひっそりと佇んでいます。見た目は苔むした古い石灯籠ですが、その周囲だけは空気が重く、ただならぬ雰囲気に満ちていると言われています。灯籠の近くには、注意を促す看板が立てられていることもあります。
- 立ち入り禁止区域 灯籠は田んぼの中にありますが、立ち入りが禁止されているわけではありません。しかし、呪いの存在を考えれば、近づくこと自体が危険な行為です。
- 安全上の注意点 この場所で最も注意すべきは、物理的な危険ではなく、呪いです。面白半分や、自分の力を過信して、灯籠に触れることは絶対にやめてください。何が起きても全て自己責任となります。
- マナー・ルール ここは呪いの伝説が残る場所です。もし訪れるのであれば、遠くからその存在を確認するに留め、決して近づきすぎたり、騒いだりしないでください。朝比奈氏をはじめ、この地に眠るかもしれない魂への敬意を忘れてはなりません。
訪問のポイント
- おすすめの時間帯 呪いの効果に時間帯は関係ないと言われていますが、心霊スポットとしての雰囲気が増すのはやはり深夜です。しかし、暗闇の中では誤って灯籠に近づきすぎてしまう危険性もあります。
- 特定のスポット 全ての恐怖は、石灯籠そのものに集約されています。